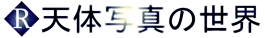木星状星雲 NGC3242
- Previous photo: M88 銀河
- Next photo: NGC3079 銀河
木星状星雲 NGC3242
NGC3242は、うみへび座に位置する惑星状星雲で、 天王星を発見したウィリアム・ハーシェルが1785年に見つけました。 NGC3242の視直径は、41″×34″程の大きさで、特に大きな惑星状星雲ではありませんが、 木星状星雲という愛称で、天文ファンに広く知られています。
NGC3242を木星状星雲と名付けたのは、イギリスの海軍士官から天文学者になったウィリアム・ヘンリー・スミスです。 NGC3242の大きさや色、見え方が木星に似ていたためと伝えられていますが、 写真に撮ると木星とは色合いが異なります。 どちらかというと、NGC3242星雲の内部は人間の瞳のように見え、 海外で名付けられている「目玉星雲(The Eye Nebula)」の愛称の方がしっくりくる気がします。
NGC3242の視等級は9等級ですが、淡く広がる散光星雲と異なり、はっきりした明るさがあるため、 天体望遠鏡を使用すれば、都会の明るい夜空でも姿を確認することができます。 ただ視直径が小さいため、NGC3242をそれなりの大きさで観察しようと思えば、 口径がある程度大きな天体望遠鏡(15センチ以上)と100倍程度の倍率が必要です。
このNGC3242の写真は、光害の激しい自宅から口径25センチの天体望遠鏡を使用して撮影しました。 被写体の南中高度が低いため、低空の悪気流の影響で、若干星が流れ気味になりましたが、 星雲の大きな構造は捉えることができました。 今回、撮影用カメラには、センサーサイズの小さな天体撮影用冷却CCDカメラを使用しましたが、 惑星撮影用動画カメラで撮影すれば、更に拡大率を上げられるため、星雲の詳細構造を捉えられるかもしれません。 また機会があれば、いろいろなカメラで撮影してみたい対象です。
Imaging information
撮影鏡筒:タカハシ Mewlon-250CRS
天体望遠鏡の架台:ヘラクレス赤道儀
使用カメラ:SBIG ST2000XM、Astronomik Type2C LRGBフィルター
露出時間:L画像=1分×32枚、RGB画像=各1分×4枚
画像処理ソフト:ステライメージ8、PhotoshopCC 2017
撮影場所:兵庫県宝塚市、2020年撮影