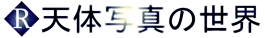セレストロン天体望遠鏡の特徴
セレストロン製の天体望遠鏡を使った印象や、メーカーの特徴をまとめたページです。 作者の見解や印象も入っていますので、軽い気持ちで読んでいただければ幸いです。
セレストロン天体望遠鏡
セレストロン(Celestron)は、アメリカのカリフォルニア州に本社を構える天体望遠鏡メーカーであり、 世界有数の天体望遠鏡メーカーの一つです。 日本では、株式会社サイトロンジャパンが総代理店になっています。
セレストロンと言えば、シュミットカセグレン望遠鏡が有名です。 セレストロンは、世界で初めて、シュミットカセグレン式の望遠鏡を量産したメーカーで、 特にオレンジ色の鏡筒のセレストロンC8は、同社のシンボルとも言える存在です。
同じくシュミットカセグレン式を製造・販売しているミード社と比較、検討されることが多く、 過去には、特許問題等でもめたこともあります。
安定した人気のシュミカセ
 シュミットカセグレン式の望遠鏡のことを、日本では「シュミカセ」と呼んでいます。
セレストロンの現在の製品ランナップでは、初心者用として、小型の反射望遠鏡や屈折望遠鏡も取り扱っていますが、
製造販売の中心は、昔から変わらずシュミカセです。
シュミットカセグレン式の望遠鏡のことを、日本では「シュミカセ」と呼んでいます。
セレストロンの現在の製品ランナップでは、初心者用として、小型の反射望遠鏡や屈折望遠鏡も取り扱っていますが、
製造販売の中心は、昔から変わらずシュミカセです。
セレストロンのシュミカセといえば、セレストロンの「C」が頭文字に付けられたシリーズが有名です。 このシリーズの数字は、口径の大きさをインチで表しており、オレンジ鏡筒でよく知られているC8は、 口径8インチ(20センチ)のシュミカセ望遠鏡となります。 最大の望遠鏡は、口径35センチのセレストロンC14望遠鏡で、重さ23キロの大型望遠鏡です。
セレストロンのシュミカセは、昔から安定した人気があります。 コンパクトで取り回しのよいシュミカセは、大口径が欲しいが、 持ち運びや収納場所を考えると、大きな望遠鏡を購入できないという日本のユーザーにぴったりでした。 1990年前後は、シュミカセブームとも呼べる時代で、 望遠鏡販売店がセレストロン社と協力して、オリジナルのシリーズを販売していました。
同じシュミカセを製造しているミードと比べたとき、セレストロンの魅力は、口径のラインアップの豊富さと、 鏡筒単体で購入できる点ではないでしょうか。 ライバル企業のミード社も、鏡筒本体だけで購入できることがありますが、 昔から、自動導入機能が付いた架台とのセットで販売されることが多かったように思います。 また、セレストロンのシュミカセは、天文ショップではビクセン製の赤道儀とセット販売されていたことも多く、 それが日本での普及に繋がったのかもしれません。
また、シュミカセは、大口径の割には安価で手に入れられるという点も魅力の一つでした。 現在のC14の価格は、円安の影響もあり、100万円近くと非常に高価ですが、 1990年頃は60万円ほどと安く、惑星撮影や銀河の撮影を楽しむユーザーから人気がありました。
写真性能を高めたシュミカセ
安定した人気を誇るセレストロンのシュミカセですが、ユーザーからは、 「シュミカセの像は甘い」という意見が聞かれるようになりました。 これは望遠鏡の光軸がずれていたことによる場合が多く、 光軸がずれやすい光学系と言えるかもしれません。
また、天体写真ファンからは、シュミカセのミラーシフトが嫌われ、それを低減するパーツなども販売されました。 私もセレストロンC8を天体撮影に使っていましたが、筒内気流が収まりにくい、 ミラーシフトが起こるなどの問題があり、主に観望用に使うようになりました。 実際、シュミカセは観望用の天体望遠鏡という位置づけになりつつありました。
セレストロンは、このようなユーザーの意見に対応するため、 副鏡に補正レンズを組み込んだ、新しいタイプのシュミカセ「Edge HD」シリーズを開発しました。 このEdge EDは、シュミカセの弱点だった周辺像の甘さを解消した望遠鏡で、 その他にもファンを備えるなど、上記の不満点を解消しています。
しかし、残念ながら、シュミカセの性能を高めたEdge HDシリーズは、日本での人気はそれほど高くないようです。 これはこの製品自体の問題というよりも、他に安価で性能の良い光学系があるためと思われます。 シュミカセが全盛のときに登場していれば、もっと注目を浴びたのではないでしょうか。
デジタル時代のセレストロンRASA
銀塩フィルムが全盛の頃、シュミットカメラという明るい写真鏡筒がありました。 ベテラン天体写真ファンから支持を集めていましたが、デジタル時代になって姿を消しました。
そんな折、セレストロンからシュミットカメラの技術を応用した「RASA」が登場しました。 RASAは、補正光学系を追加することにより、シュミットカメラで問題とされていた、 焦点面が球面になる問題を解消した光学系です。 通常の望遠鏡と異なり、デジタルカメラは望遠鏡開口部に取り付けます。 観望には使えず、写真撮影専用の天体望遠鏡(アストログラフ)です。
セレストロンRASAの口径は、11インチ(約28センチ)で焦点距離は620mmです。 計算上は明るさがF2.2と、高性能の超望遠レンズよりも明るい仕様です。
天体撮影に大変魅力的な仕様のセレストロンRASAですが、望遠鏡の筒先にデジタルカメラを取り付けるため、 フラット補正が正しく行えるかどうかが気になります。 また、F2.2と非常に明るいため、光軸調整の方法も気になるところです。 しかし、これだけF値が明るければ、短時間露光で、天体を写し出すことができるので、 オートガイドは必要ないかもしれません。 特に彗星のような、淡くて短時間露光が必要な天体に適した光学系だと思います。
実際に撮影地でセレストロンRASAを使っている方を見かけたことはありませんが、 天体写真ファンとしては気になる鏡筒ですね。 ユーザーの作品の数が増えてくれば、人気が出てくる望遠鏡かもしれません。