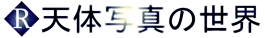�ȒP�Ȑ���B�e�̕��@�u�����Y�L�b�g�Ő�����B���Ă݂悤�v
�Œ�B�e�̊T�v�����������Ƃ���ŁA���ۂɐ�����B�e���Ă݂܂��傤�B ���̃y�[�W�ł́A�f�W�^�����t�J�����̃����Y�L�b�g�ŎB�e�����Ă̓V�̐�̎ʐ^�����ɂ��āA ���̎B�e���@���ڂ���������Ă��܂��B
���Œ�B�e�̊T�v�ɂ��Ă��Œ�B�e�̕��@�y�[�W��������������
�����Y�L�b�g�ŎB�e�����V�̐�
�B�e���@�ɓ���O�ɁA���ۂɃ����Y�L�b�g�ŎB�e�����ʐ^�����Ă݂܂��傤�B ���̎ʐ^�́A�L���m��EOSKissX3��EF-S18-55ISII�����Y�ŎB�e�����Ă̓V�̐�̎ʐ^�ł��B
�f�W�J���̊��x��ISO3200�ɐݒ肵�āA60�b�I�o�ŎB�e�����ʐ^�ł��B �g�債�Č���Ɛ��������Ă��܂����A���������Ă̓V�̐삪�Y��Ɏʂ��Ă��܂��B �����Y�L�b�g�ł�������B�e���邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ��A���킩�蒸����Ǝv���܂��B �܂��͂��̎ʐ^���Q�l�ɂ��āA�V�̐�̌Œ�B�e�Ƀ`�������W���Ă݂܂��傤�B

�B�e�@��
 ����A�B�e�Ɏg�p�����f�W�^�����t�J�����́A�L���m��EOSKissX3�ł��B
����Ƀ����Y�L�b�g�ŃZ�b�g�ɂȂ��Ă���A�L���m��EF-S18-55ISII�����Y��p���ĎB�e���܂����B
����A�B�e�Ɏg�p�����f�W�^�����t�J�����́A�L���m��EOSKissX3�ł��B
����Ƀ����Y�L�b�g�ŃZ�b�g�ɂȂ��Ă���A�L���m��EF-S18-55ISII�����Y��p���ĎB�e���܂����B
����җp�f�W�J���ƃ����Y�̃Z�b�g�́A�������i5���~�O��Ɣ��ɂ���������������܂��B �������A�����J�����ł���K�v�͂���܂���B�L���m��EOSKissX7��j�R��D5200�ł��A ���l�̕��@�ŎB�e�ł���ł��傤�B
�f�W�^���J�����̑��ɂ܂��K�v�Ȃ̂́A�J�����O�r�ł��B ���ɃJ�����O�r���������Ȃ�A�܂��͂�����g���ĎB�e���Ă݂܂��傤�B �������ꂩ�琯��B�e�p�ɍw�������̂ł�����A�u���̏o�Ȃ�������v�ȎO�r�������߂��܂��B
���̑��ɕK�v�Ȃ̂��A���莝���̃f�W�^�����t�J�����ɍ��������[�g�X�C�b�`(�����[�Y)�ł��B ���̃f�W�^�����t�J�����́A�ő��30�b�I�o�܂ł����ݒ�ł��܂���B����ȏ�̘I�o���Ԃ������鎞�ɂ́A�o���u(BULB)�@�\���g���ĎB�e���܂��B �I�o���Ԓ������ƃV���b�^�[�{�^���������Ă������Ƃ͂ł��܂���̂ŁA�V���b�^�[���Œ�ł��郊���[�g�X�C�b�`�͕K�{�ł��B
�V���ɍw������Ȃ�A�^�C�}�[�@�\���t���������[�g�X�C�b�`�������߂ł��B ���ꂪ����A�o���u�B�e���A���v���C�ɂ���K�v������܂���B �L���m��EOSKiss�V���[�Y�p�ɂ́A�A�}�]���ȂǂŔ̔�����Ă���TM-C�R���g���[���[�� �����߂ł��B�������̐��i���g���āA���̉Ă̓V�̐�̎B�e���s���܂����B
�����Y�t�[�h���ł��邾���p�ӂ��Ă����܂��傤�B �����Y�t�[�h�́A�����Y�ɓ����Ă���]�v�Ȍ����Ղ��Ă���܂��B �܂��A��I��z�R���������Y�ɕt���̂�������x�h���ł���܂��B
�K�v�Ȑ���B�e�@�ނ̃|�C���g
�@�f�W�^�����t�J������~���[���X���J�����ƃ����Y
�A��������Ƃ����J�����O�r
�B�����[�g�R���g���[���[
�C�����Y�t�[�h
������Y��ȏꏊ�ɍs����
 ����̂悤�ȉĂ̓V�̐�̎ʐ^���B��ɂ́A�����Y��Ɍ�����ꏊ�ŎB�e���Ȃ�������܂���B
�܂��́A��������x�O�ɏo�����܂��傤�B
���s�̂��łɎB�e����̂��悢�ł��傤�B
����̂悤�ȉĂ̓V�̐�̎ʐ^���B��ɂ́A�����Y��Ɍ�����ꏊ�ŎB�e���Ȃ�������܂���B
�܂��́A��������x�O�ɏo�����܂��傤�B
���s�̂��łɎB�e����̂��悢�ł��傤�B
���������Ă̓V�̐�͓�V�ŋP���Ă��܂�����A�쑤�̎��E���J�����ꏊ��I��ŎB�e���܂��傤�B ��͈Â��ł��̂ŁA���߂Ă̏ꏊ�ɂ͖��邢�����Ɍ��n�ɓ�������悤�ɂ��A����̏��m�F���Ă���B�e�ɒ��݂����Ƃ���ł��B
����̎ʐ^�̎ʂ��́A���̎��̐���̏�Ԃɑ傫�����E����܂��B �����x���ǂ��A�V�̐삪���̓I�Ɍ�����悤�Ȑ���ɏo�����A�����ŏЉ�Ă���ʐ^�����������Y��Ȏʐ^���B�邱�Ƃ��o����ł��傤�B �t�ɉ������������Ȃ�A�V�̐�͂قƂ�ǎʂ��Ă��Ȃ���������܂���B �����悤�Ɍ����鐯��ł��A���̓��ɂ���Č������͑傫���ς��܂��B �ł���Ȃ�A�����̗ǂ�����I��ŎB�e����ƁA�悢���ʂ�������ł��傤�B
�܂��A����ɂ����ӂ��܂��傤�B �����ɏƂ炳�ꂽ���͑z���ȏ�ɖ��邭�A���X�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B �ł���ΐV���̓����A�����o�Ă��Ȃ����ԑт�_���Đ�����B�e���Ă݂܂��傤�B
�B�e�ꏊ�̃|�C���g
�@������Y��ȏꏊ�ɏo������
�A�Ȃ�ׂ����E�̗ǂ��ꏊ
�B�������肪���Ȃ��V���O��̎������x�X�g
�f�W�J���̐ݒ�
 �܂��̓f�W�^���J�����̃��[�h���A�}�j���A�����[�h�ɐݒ肵�܂��傤�B
�����āA�V���b�^�[�X�s�[�h���o���u�ɂ��A���x���Ȃ�ׂ��������Ă����܂�(����̎ʐ^�ł�ISO3200)�B
�����Y�̃I�[�g�t�H�[�J�X�̓}�j���A��(MF)�ɂ��āA��Ԃ�h�~���u�����Ă����܂��傤�B
�܂��̓f�W�^���J�����̃��[�h���A�}�j���A�����[�h�ɐݒ肵�܂��傤�B
�����āA�V���b�^�[�X�s�[�h���o���u�ɂ��A���x���Ȃ�ׂ��������Ă����܂�(����̎ʐ^�ł�ISO3200)�B
�����Y�̃I�[�g�t�H�[�J�X�̓}�j���A��(MF)�ɂ��āA��Ԃ�h�~���u�����Ă����܂��傤�B
���ɉ掿�Ȃǂׂ̍��Ȑݒ���s���܂��B �L�^�掿�́ARAW���[�h�������߂ł��B JPEG���[�h�ł������悤�ɎB�e�ł��܂����A�����B���ĉ摜�������鎞�̂��߂�RAW���[�h�ŎB�e���邱�Ƃ������߂��܂��B �Ȃ��ARAW�摜��JPEG�摜���ɋL�^�ł���f�W�J�������g���Ȃ�A���̉掿���[�h���g���ĎB�e���Ă݂܂��傤�B
�z���C�g�o�����X�́A�I�[�g�ł��܂��܂���B �s�N�`���[�X�^�C���̓V���[�v�l�X��������Ȃ������ݒ肪�����߂ł��B �F��Ԃ́A�摜�������s���Ȃ�AdobeRGB�ł��悢�ł����A��ʓI�ɂ�sRGB�ɐݒ肵�Ă����܂��B
���̑��ɂ́A�J�����̃J�X�^���@�\�̒��ɂ���u�����ԘI���̃m�C�Y�ጸ�v���I���ɂ��Ă����܂��傤�B ��������ƁA�I�o��Ƀm�C�Y�摜���J�����������I�Ɏ擾����̂ŁA�I�o���Ԃ��Q�{������܂����A �m�C�Y�����炷���Ƃ��ł��܂��B �܂��͂��̃��[�h���I���ɂ��ĎB���Ă݂܂��傤�B
�u�����x�̃m�C�Y�ጸ�v�Ƃ����@�\�ɂ��ẮA����́u�ア�v�������߂ł��B �����x�m�C�Y�ጸ�������K�p����ƁA�ʂ��Ă��鐯���m�C�Y�Ɗ��Ⴂ���āA���̐��������Ă��܂��܂��B
�f�W�J���ݒ�̃|�C���g
�@�B�e���[�h�́u�}�j���A���v�B�V���b�^�[���x�́u�o���u�v
�AISO���x�́AISO3200�ɐݒ�
�B�����Y�́u�}�j���A���t�H�[�J�X�v�A��Ԃ�h�~���u�́uOFF�v
�CRAW�{JPEG���[�h��������
�D�����ԃm�C�Y�ጸ�̓I��
�E�����x�m�C�Y�̒ጸ�@�\�͎�
���C�u�r���[�Ńs���g�����킹�悤
 ���ɁA�J�����O�r�Ƀf�W�^�����t�J�������Œ肵�āA�s���g�����킹�܂��傤�B
�}�j���A���ł̃s���g���킹�͏��X�ʓ|�ł����A���܂�_�o���ɂȂ炸�ɂ�����荇�킹�Ă݂܂��傤�B
���ɁA�J�����O�r�Ƀf�W�^�����t�J�������Œ肵�āA�s���g�����킹�܂��傤�B
�}�j���A���ł̃s���g���킹�͏��X�ʓ|�ł����A���܂�_�o���ɂȂ炸�ɂ�����荇�킹�Ă݂܂��傤�B
�܂��A�J���������Y�̃Y�[�����L�p���ɌŒ肵����A�s���g�����O�����ɂȂ�悤�ɉ܂��B �����āA���▾�邢�ꓙ���Ȃǂ��t�@�C���_�[�̒����ɓ������܂��B ������A���C�u�r���[�@�\���I���ɂ��܂��B
���C�u�r���[�@�\���I���ɂ���ƁA�t�����j�^�[�̒����ɁA���������������������������ʂ��Ă���Ǝv���܂��B ���̉摜���g��{�^���������āA�g�債�Ċm�F���܂��B �g�傳�ꂽ�摜�����Ȃ���A�s���g�����O���A���⌎����ԏ������Ȃ�ʒu��T���܂��B ����͌Œ�B�e�Ȃ̂ŁA���܂莞�Ԃ������Ă���ƁA���������ĉ�ʂ��瓦���Ă����Ă��܂��܂��B �葁���s���܂��傤�B
���C�u�r���[�@�\���Ȃ��f�W�^�����t�J�����̏ꍇ�ɂ́A�Z���I�o���ԂŃe�X�g�B�e���Ă݂�Ƃ悢�ł��傤�B ���������ɖ�i�Ȃǂ�������ꍇ�ɂ́AAF�@�\���g���ăs���g���킹���Ă���A�}�j���A���ɖ߂��Ă݂Ă͂������ł��傤�B
�����Y�̃s���g����������A�B�e���Ɍ���ăs���g�����O���Ă��܂�Ȃ��悤�ɁA
�e�[�v�Ńs���g�����O���Œ肵�Ă����܂��傤�B
���ڂ����s���g���킹�̕��@�́A�s���g���킹�̕��@�y�[�W�������������B
�s���g���킹�̃|�C���g
�@�����Y�̃Y�[�����Œ�
�A���▾�邢�����t�@���_�[�̒����֓���
�B���C�u�r���[�@�\���I��
�C���̕������g��
�D���̑�����ԏ������Ȃ�悤�Ƀs���g�����O����
�E�s���g����������A�s���g�����O���e�[�v�ŌŒ�
�\�}�����킹�悤
���ɎB�e����\�}�����킹�܂��傤�B ����͐���̎ʐ^�ł��̂ŁA�������ʂ̑唼�ɂ��ĎB���Ă݂Ă͂������ł��傤�B �v�����āA��ʂ̏�W�����x��Ɋ��蓖�Ă�Ƃ悢�ł��傤�B
�J���������Y�̃Y�[�����L�p���ɂȂ��Ă��邩�A������x�m�F���܂��傤�B ����̃����Y�L�b�g�̏ꍇ�A18�~�����L�p���ł��B �L����p�ŎB���������A�Œ�B�e�ł����̗��ꂪ�킩��ɂ����Ȃ�܂��B �܂��A�����Y�̍i��͊J��(�ł����邢��)�Ŏʂ��Ă݂܂��傤�B
�J�����̃t�@�C���_�[�z���ł́A���͈Â��ĕ�����Â炢�ł����A���邢���𗊂�ɍ\�}�����킹�܂��B ��O�̖Ȃǂ�ڈ��ɂ��Ă��悢�ł��傤�B �\�}�������悻�������Ǝv������A���b�I�o�Ńe�X�g�B�e���Ă݂āA�v���ʂ�̍\�}�ɂȂ��Ă��邩���m�F���Ă݂܂��B ����Ă�����A�f�W�J�������炵�čēx�B�e���āA�\�}��ǂ�����ł����܂��傤�B
�{�B�e�O�ɂ́A�f�W�J���̐ݒ��������x�m�F���Ă܂��傤�B �J�����̐ݒ肾���ł͂Ȃ��A�J�����O�r�͂�������Ɛݒu����Ă��邩�B�R���g���[���[�̓J�����Ɍq����Ă��邩���A �B�e�O�Ɋm�F����Ȃ�����Ɛ���B�e�̎��s�����Ȃ��Ȃ�܂��B
�\�}���킹�̃|�C���g
�@�������ʂɑ傫�������
�A���邢����ڈ��ɍ\�}�������悻���킹��
�B���b�I�o�Ńe�X�g�B�e���Ċm�F
�B�e�J�n
 �^�C�}�[�����[�g�R���g���[���[������A�I�o���Ԃ�60�b�A�B�e������1���ɂ��ĎB�e���Ă݂܂��傤�B
���ʂ̃����[�g�X�C�b�`�ł́A���v�����Ȃ��炨�悻60�b�ɂȂ����Ƃ���ŁA�V���b�^�[�{�^�������𗣂��܂��B
����̓m�C�Y���_�N�V������������̂ŁA2���Ԃ̓J�����ɐG��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B
�^�C�}�[�����[�g�R���g���[���[������A�I�o���Ԃ�60�b�A�B�e������1���ɂ��ĎB�e���Ă݂܂��傤�B
���ʂ̃����[�g�X�C�b�`�ł́A���v�����Ȃ��炨�悻60�b�ɂȂ����Ƃ���ŁA�V���b�^�[�{�^�������𗣂��܂��B
����̓m�C�Y���_�N�V������������̂ŁA2���Ԃ̓J�����ɐG��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B
�f�W�J���̐ԃ����v�������āA�m�C�Y���_�N�V�������I�������A�B�e�摜���t�����j�^�[�Ŋm�F���Ă݂܂��傤�B �Ă̓V�̐�͎ʂ��Ă���ł��傤���B �摜���g�債�Ă݂āA�����ڂ��Ă���ꍇ�́A�s���g������Ă���̂�������܂���B �s���g��������x���킹�����܂��傤�B �\�}������Ă���ꍇ�́A�J�����̕����������������Ē������܂��傤�B
�f�W�^�����t�J�����̂悢�Ƃ���́A�B�e�����摜�������ɉt�����j�^�[�Ŋm�F�ł��邱�Ƃł��B �I�o���Ԃ⊴�x��ς��Ă݂āA�������[���ł���܂ŎB�e���Ă݂܂��傤�B ���s���낵�Ă��邤���ɁA���ɐ�����B��R�c���킩���Ă���Ǝv���܂��B
������B��Ƃ����ƁA�������ʂȃJ��������Y���K�v�Ƃ����C���[�W����������ł����A �f�W�J���ƃZ�b�g�̃����Y�ł��A�Y��Ȑ�����B�e�ł��邱�Ƃ��������蒸�����Ǝv���܂��B �����Y��Ɍ�����ꏊ��K�ꂽ���ɂ́A����F������Œ�B�e�Ƀ`�������W���Ă݂Ă��������B
�{�ԎB�e�̃|�C���g
�@�f�W�J���̐ݒ���ēx�m�F
�A�����[�g�R���g���[���[���g���ĘI�o�J�n
�B�B�e�I����A�B�e�摜�����j�^�[�Ŋg�債�ăs���g������Ă��Ȃ������m�F
���낢��ȎB�e���@
��̎ʐ^�ł́A���x��ISO3200�ɂ��āA�I�o���Ԃ�60�b�ƒZ�����邱�ƂŁA����������ڂ̂悤�Ɏʂ��Ă݂܂����B �Œ�B�e�ł́A���̑��ɂ��A�I�o���Ԃ����āA������̂悤�Ɏʂ����@������܂��B �ǂ��炩�Ƃ����ƁA������̕����Œ�B�e�Ƃ��Ă͈�ʓI�ł����B �≖�t�B�����̍��́A���̂悤�ȎB�e���@���قƂ�ǂ��������߂ł��傤�B
�B�e���@�͊ȒP�ł��BISO��800��400�ɂ��āA�I�o���Ԃ����܂��B �����������قǁA���͗���Đ��̒����������Ȃ�܂��B
���̎ʐ^�́A�f�W�J���̊��x��ISO400�ɂ��āA8���I�o�ŎB�e�����Ă̓V�̐�ł��B ��̎ʐ^�ƌ���ׂ�ƁA��������Ă���̂��킩��܂��B

�����x�m�C�Y�����Ȃ��f�W�^�����t�J���������g���Ȃ�AISO���x��12800�Ȃǂɐݒ肵�āA�����ƒZ���I�o���ԂŎB�邱�Ƃ��\�ł��B ��������A�قƂ�ǐ�������Ă��Ȃ��ʐ^���B�邱�Ƃ��o����ł��傤�B
����_���Ɏʂ����߂̘I�o����
 �Œ�B�e�ł́A�I�o���Ԃɔ�Ⴕ�Ďʂ鐯�̋O�Ղ������Ȃ��Ă����܂��B
�܂������I�o���Ԃł��A�����Y���]���ɂȂ�قǐ��̓������g�傳���̂ŁA���̋O�Ղ͒����̂тĎʂ�܂��B
�Œ�B�e�ł́A�I�o���Ԃɔ�Ⴕ�Ďʂ鐯�̋O�Ղ������Ȃ��Ă����܂��B
�܂������I�o���Ԃł��A�����Y���]���ɂȂ�قǐ��̓������g�傳���̂ŁA���̋O�Ղ͒����̂тĎʂ�܂��B
�Œ�B�e�ł��A������x�̘I�o���ԓ��Ȃ琯�̈ړ�������قǖڗ������A�����قړ_���Ɏʂ��Ă���܂��B ���̐���_���Ɏʂ����߂̍ő�̘I�o���Ԃ́A�����Y�̏œ_�����Ǝʂ������Ō��܂�܂��B �����Y�̏œ_�������Z���قǁA�܂��V�̖k�ɕt�߂��ʂ��قǁA�����I�o���Ԃł����͓_���Ɏʂ��Ă���܂��B
�V�̖k�ɂɋ߂��قǒ����I�o���Ԃ���������̂́A�k�ɐ��ɋ߂Â��قǐ��̓������������Ȃ邩��ł��B �t�ɃI���I�����̂悤�ɓV�̐ԓ��߂��Ɉʒu���Ă��鐯���͓����������A�Z���I�o���Ԃł�����Ďʂ�₷���Ȃ�܂��B
���x���A�b�v�@��
��I�����q�[�^�[
���Ԃ������ĉ���������ʐ^���B���Ă���ƁA�����Y�ɖ�I�����Ă��邱�Ƃ�����܂��B ���{�͎��x�������̂ŁA��I�͐���B�e�ł͔������Ȃ����ŁA�����̓V���t�@���̓����Y�Ƀq�[�^�[�������Ė�I�̕t����h�~���Ă��܂��B
���͐̂Ȃ���̋ˊD�J�C����DC12V�œ����q�[�^�[�������Y�Ɋ����Ďg���Ă��܂����A �v�̓����Y���������߂Ă�����Ζ�I�h�~�ɂȂ�̂ŁA���낢��H�v����Ă݂Ă͂������ł��傤�B �Ⴆ�A�G�l���[�v�̏[�d���J�C���������Y�Ɋ����Ďg���Ă݂�ƌ��ʂ������邩������܂���B
�����Y�t�[�h
����̎B�e�ł́A�����Y�t�[�h���g�킸�ɎB�e���܂������A�t�[�h�͐���B�e�ɂ����ĕK�{�ƌ�������̂ł��B �t�[�h���Ȃ��ƁA�Ԃ̃��C�g�Ȃǎv��ʏ�����̌����A�ʂ荞��ł��Ă��܂��܂��B �����Y�L�b�g�̃����Y�ł́A�I�v�V�����ݒ�ɂȂ��Ă��܂����A�ł��邾���������낦�������悢�ł��傤�B
�\���o�b�e���[
����̎B�e�ł͒����ԘI������̂ŁA�f�W�J���̃o�b�e���[���ʏ�����������Ղ��܂��B �܂��A������Y��ȏꏊ�͕W���������A�C�����Ⴂ���Ƃ������̂ŁA�o�b�e���[�̃p���[�������Ă��܂��܂��B �ˑR�̃o�b�e���[��ɑΏ����邽�߂ɂ��A�\���̃o�b�e���[�p�b�N�𑽂߂Ɏ����Ă����������悢�ł��傤�B
������
�J���������Y�����炾���łȂ��A�t�@�C���_�[��������������荞�ނ��Ƃ�����܂��B ����B�e�ł́A�����ԎB�e���ɃJ�������痣��邱�Ƃ������̂ŁA�t�@�C���_�[����̖�����͏d�v�ł��B
�A�C�s�[�X�V���b�^�[����������Ă���f�W�J���ł́A������g���悤�ɂ��܂��傤�B ���̑��̋@��ł́A�B�e�J�n�O�Ƀt�@�C���_�[�������z�Ȃǂŕ����悤�ɂ���Ƃ悢�ł��傤�B ���́A�I�����A�t�@���_�[�ɍ����p�[�}�Z���e�[�v��\��悤�ɂ��Ă��܂��B
�\�t�g�t�B���^�[
���邢����ڗ������邽�߂ɁA�P���R�[�̃v���g���t�B���^�[�Ȃǂ��g���ĎB�e������@������܂��B ���̂悤�ȃ\�t�g�t�B���^�[���g���ƁA�����ɂ���Ō��z�I�Ɏd�オ��܂����A���邳���Â��Ȃ�̂ŁA��蒷���I�o���Ԃ��K�v�ƂȂ�܂��B
�ǂ��炩�Ƃ����ƁA�|�[�^�u���ԓ��V���g�����ǔ��B�e�ł悭�g�p�����@�ł��B �������g���ɂȂ�Ȃ�A�t�B���^�[�̖����ɂ���Đ��̂ɂ�����قȂ�܂��̂ŁA�w������O�ɓV�������Œ��ׂ������悢�ł��傤�B
���邢�����Y
�J��F�l�̖��邢�J���������Y���g���ƁA�I�o���Ԃ�Z�����邱�Ƃ��ł���̂ŁA�\�����@���g����܂��B ���邢�����Y�͍����Ȃ̂ŁA�ŏ����瑵����K�v�͂Ȃ��Ǝv���܂����A ����B�e�Ɋ���Ă��āA�u�������Y��Ɂv�Ǝv��ꂽ��w�����������Ă݂Ă͂������ł��傤���B
 |
Kenko PRO1D �v���\�t�g�� A 58mm
�P���R�[PRO1D �v���\�t�g��A�́A����B�e�ɐl�C�̂���\�t�g�t�B���^�[�ł��B �s��ɂ͑��ɂ��l�X�ȃ\�t�g�t�B���^�[���̔�����Ă��܂����A�P���R�[�̂��̃\�t�g�t�B���^�[���ł��l�C������܂��B �≖�t�B�����̍��́A�ǂ�ȃt�B���^�[�ł������ł��錋�ʂ������܂������A �f�W�^���ɂȂ��Ă���́A���w���\���Ⴂ�t�B���^�[���g���ƁA�������тɕό`���Ă��܂����Ƃ�����܂��B ���̓_�A���̃v���\�t�g��A�ɂ́A���������}�C�i�X�ʂ��Ȃ��A���S���Đ���B�e�Ɏg�p���邱�Ƃ��ł��܂��B �����g�����̃t�B���^�[�����̎B�e�Ɏg�p���Ă��܂��B �����Y�̏œ_�����ɂ���ẮA�P���̃{�P�ʂ���傫���������邱�Ƃ����邽�߁A ���[�t�B���^�[���g�����Ƃ�����܂��B �����Y���ɔ��������ƌ��\�ȏo��ɂȂ�̂ŁA�t�B���^�[�a�̑傫�ȃT�C�Y���w�����āA �X�e�b�v�A�b�v�����O�ƕ��p���Ďg�p���Ă��܂��B |