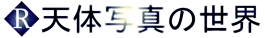ガイド撮影の方法
天体望遠鏡を使った天体撮影の世界では、数百から数千ミリの焦点距離で遠く離れた天体を撮影します。 拡大率が高いため、星を自動で追尾する赤道儀を使っても、星の動きとのズレが生じて、星が線状に写ってしまいます。 そのため、星を完全な円形に写そうと思うと、そのズレを補正しながら撮影する必要があります。
このズレを補正することを、一般的に「ガイド補正」とか単に「ガイド」と呼んでいます。 そして、ガイド補正をしながら撮影する方法を「ガイド撮影」といいます。 ここでは、ガイド撮影の方法について、なるべく分かりやすく説明しています。
なお、現在ではオートガイダーが一般的になったので、 オートガイド撮影のことを略して「ガイド撮影」と呼ぶことが多くなりましたが、 このページでは、眼視ガイドとオートガイドを別々に分けてご紹介しています。
ガイド撮影が必要となる焦点距離
 使用している赤道儀の追尾精度にも左右されますが、
焦点距離が150ミリ前後のカメラレンズや短焦点望遠鏡を使った撮影なら、ガイド補正は必要ありません。
拡大率が低いため、追尾が若干ずれていても星は点像に写るでしょう。
使用している赤道儀の追尾精度にも左右されますが、
焦点距離が150ミリ前後のカメラレンズや短焦点望遠鏡を使った撮影なら、ガイド補正は必要ありません。
拡大率が低いため、追尾が若干ずれていても星は点像に写るでしょう。
一方、それ以上に焦点距離の長い望遠レンズや、天体望遠鏡を使った直焦点撮影になると、 どうしても小さな追尾のズレが写真に影響してきます。 ガイド補正を行わないと、本来は丸く写る星が、流れて短い線のように写ってしまいます。
ガイド撮影に必要な機材
 ガイド撮影は右写真のように、一つの赤道儀に2本の望遠鏡を載せて行います。
左側の望遠鏡が撮影用の鏡筒。右側が追尾状況を監視するために追加した望遠鏡です。
ガイド撮影は右写真のように、一つの赤道儀に2本の望遠鏡を載せて行います。
左側の望遠鏡が撮影用の鏡筒。右側が追尾状況を監視するために追加した望遠鏡です。
撮影用の望遠鏡には、デジタル一眼レフカメラや天体用CMOSカメラが取り付けられていますので、 星のズレを撮影中確認することができません。 そこで、監視用の望遠鏡が追加で必要になります。 監視用の望遠鏡は「ガイド鏡」と呼ばれ、撮影用望遠鏡と同じ架台に載せられます。
ガイド鏡は、ガイドを監視するだけですから、高価な製品は必要ありません。 鏡筒が大きいと風の影響も受けるため、焦点距離400~600ミリぐらいの屈折望遠鏡が適しています。 ガイド鏡は、ガイドマウントと呼ばれる微動機能が付いた小さな雲台に載せて同架することが多いです。
ガイド鏡やガイドマウントは、赤道儀にしっかりと取り付けることが大切です。 ガイド鏡自体がフラフラしたら、赤道儀の動きを監視する意味がなくなってしまいます。
ガイド撮影には、ガイドを監視する目が必要です。 人間がガイド鏡を覗き、追尾状況を確認する方法を「眼視ガイド」と呼んでいます。 眼視ガイドには、ガイド用アイピースと呼ばれる接眼レンズ、もしくは接眼アダプターが必要です。 このガイド用アイピースの視野内には、十字線が設けられていて、 星が当初の位置からずれたことを客観的に認識できるようになっています。 この種類のアイピースで一番の定番製品は、ビクセンGA4ガイドアダプターです。
人間の眼の代わりに、カメラが星のズレを監視する方法もあります。 これは「オートガイド」と呼ばれていて、現在の天体写真ガイド撮影の主流になっていますが、 オートガイドを行うためのデジタルカメラ(オートガイダー)が必要ですので、ある程度のコストがかかります。
眼視ガイド撮影の実際
 ガイド撮影の様子をご理解いただくため、実際の手順を具体的に見て行きましょう。
まずは、ビクセンGA4アダプターを使った眼視ガイドについて説明しています。
ガイド撮影の様子をご理解いただくため、実際の手順を具体的に見て行きましょう。
まずは、ビクセンGA4アダプターを使った眼視ガイドについて説明しています。
すべての機材の設置が終わったら、撮影用望遠鏡を被写体に向けます。 もちろん極軸をしっかり合わせて、デジカメのピントも合わして、撮影望遠鏡の構図も調整しておきます。 赤道儀の電源も入っていて、いつでも撮影開始できる状態です。
このままシャッターを切ってしまうと、赤道儀に任せた撮影になってしまいます。 シャッターを切る前に、赤道儀に同架しているガイド鏡だけを、撮影対象近くの明るい星に向けます。 この時に赤道儀のモーターを動かしてしまっては、撮影望遠鏡の構図もずれてしまいますので意味がなくなります。 ガイドマウントの微動装置を動かして、ガイド鏡だけをガイドに使う星(ガイド星)に向けましょう。
初めは、低倍率のアイピースを使って、ガイド星を探すのがお勧めです。 ガイド補正自体は、高い倍率で行った方が精度が上がりますが、 初めから高倍率アイピースを使用すると、ガイドに適した明るい星が見つかりません。 星が視野の中央に入ってから、高い倍率のアイピースに変更しましょう。
 星がガイド鏡の視野に入ったら、ガイドアダプターGA4の電源を入れて、スケールパターンが見えるようにします。
星がガイド鏡の視野に入ったら、ガイドアダプターGA4の電源を入れて、スケールパターンが見えるようにします。
次にスケールパターンを移動させて、ガイド星をスケールの中央や十時になっている点に位置させます。 こうすると、星のズレが見ていてすぐわかるようになります。 ここまで来れば、ガイド撮影の準備は完了です。静かにデジカメのシャッターを切りましょう。
シャッターを切った後は、ガイド鏡の星を監視します。 星がスケールパターンの線からずれたら、赤道儀のモーターのボタンを押して、星を十字線の中央に戻してやります。 撮影時間中、これを繰り返し行って、ガイド星が同じ場所に留まるようにします。 少し根気のいる作業ですが、追尾精度の良い赤道儀なら、1分に一度確認する程度で大丈夫でしょう。
もし、撮影開始後、ガイド星がすぐに大きくずれる場合は、赤道儀の設置に問題があると考えられます。 極軸設定や設置方法を再確認し、問題がなければ、モーターや赤道儀のギアに故障や損傷がないか確認してみましょう。
オートガイド撮影
 銀塩フィルムを使用していた頃、長年、眼視ガイドで撮影していましたが、一晩中、
星を監視するのは根気がいる作業で、寒い冬の夜は指先が痛くなるほどでした。
銀塩フィルムを使用していた頃、長年、眼視ガイドで撮影していましたが、一晩中、
星を監視するのは根気がいる作業で、寒い冬の夜は指先が痛くなるほどでした。
いつか電子的に補正してくれる機器が発売されないかと思っていたところ、 その苦労を減らしてくれるオートガイダーという機械が、1990年に登場しました。 スタートラッカーと呼ばれたSBIG社のST-4の登場です。
オートガイダーとは、人間の眼の変わりにガイド星を監視してくれる機器のことです。 星を監視し、赤道儀のモーターのボタンを押すという動作を自動で行ないます。 実際には、CCDやCMOSセンサーで星の光を受け、そのずれをソフトウェアが監視し、 赤道儀に補正信号を送るという一連の動作を行なう機器です。
オートガイダーの基本的な原理は、眼視ガイドと同じです。 ガイドアイピースの代わりに、オートガイダーのカメラ部分をガイド鏡の接眼部に取り付けます。 また、赤道儀に補正信号を送らなければいけませんので、 オートガイダーと赤道儀を結ぶ専用ケーブルが必要になります。
オートガイダーには様々な種類があります。 Webカメラとフリーのオートガイドソフトを使った安価なものから、 果ては冷却CCDカメラを使った高性能の製品まで存在します。 どれもそれぞれ特徴がありますが、予算と合わせて検討するとよいでしょう。
オートガイダーがあれば、撮影中も望遠鏡に張り付いている必要がありません。 撮影中、双眼鏡で星空を見たり、星仲間と会話を楽しむことができます。 少しコストがかかってしまいますが、これから天体写真撮影を本格的に楽しむなら、オートガイダーを使ったオートガイド撮影がお勧めです。 詳しくは、初めてのオートガイド撮影、または、オートガイドの方法のページをご覧下さい。
ガイド撮影の変遷
 今の赤道儀は電動追尾が当たり前ですが、
1970年頃までは、モーターさえ付属しておらず、手で微動ハンドルを回して星を追尾する「手動ガイド」が一般的でした。
人間の手では追尾精度に限界があったため、50ミリ前後の標準レンズで撮影するのが精一杯でした。
今の赤道儀は電動追尾が当たり前ですが、
1970年頃までは、モーターさえ付属しておらず、手で微動ハンドルを回して星を追尾する「手動ガイド」が一般的でした。
人間の手では追尾精度に限界があったため、50ミリ前後の標準レンズで撮影するのが精一杯でした。
1970年中頃になると、天体望遠鏡メーカーから個人向けのモータードライブが発売されはじめます。 しかし、モーターにサーボモーターやシンクロナスモーターが使われた当時のモーターは、 コントローラーが大きく、また非常に高価でした。 そのため、モータードライブを購入できるのは一部のユーザーに限られました。
1980年頃になると電子機器の発展と共に、 ステッピングモーターを用いた小型で比較的安価なモータードライブが登場し、 誰もがオプションとして購入できるようになりました。 しかし、この頃はまだ赤緯が部分微動の機種も多く、両軸にモーターを取り付けられた赤道儀は一部の機種のみでした。 そのため、赤経方向の修正はモーターボタンを使い、赤緯に星がずれたときは、微動ハンドルを回して修正していました。
1980年中頃になると、バブルに発した好景気の影響もあり、天体望遠鏡業界も賑わいます。 両軸モーター内蔵の赤道儀が次々と発表され、微動ハンドルは過去のものとなりはじめました。 高橋製作所やビクセンをはじめ、ペンタックス、ケンコーやカートンからも望遠鏡が販売されていました。 ハレー彗星が回帰した影響もあり、天文業界が最も華やいだ時代だったと思います。
1990年にSBIG社から、オートガイダーST-4が発売され、オートガイド追尾の時代へ突入しました。 しかし、当時のオートガイダーは価格が高く、一部のハイアマチュア以外は眼視ガイドで撮影を楽しんでいました。
2000年に入ってしばらく経った頃、 海外天文誌で、MEADE DSIカメラとパソコンを使った安価なオートガイドシステムが紹介されました。 これが反響を呼び、各社赤道儀と繋ぐ基盤が個人で製作されるようになりました。
その後、Webカメラがオートガイダーとして使用されるようになり、 天文ショップからオリジナルのオートガイドコントローラー「ガイドウォーク」などが発売されるようになりました。 この頃になると価格も下がり、やっと誰もがオートガイド撮影が楽しめるようになったと言えます。
2010年を過ぎると、SBIG社から小型のオートガイダーST-iが登場します。 業務カメラ用のCマウントレンズを取り付けたオートガイドシステムは、天体写真ファンの注目を集めました。
ちょうどPHD Guidingと呼ばれる、フリーのオートガイドソフトウェアが登場していたこともあり、 カメラをQHY CCD社に変更したより安価なシステムが、天文ショップから販売されるようになりました。
2015年、協栄産業からラセルタMGENオートガイダーが発売開始されました。 それまでのQHY CCDカメラを使用したオートガイドシステムとは異なり、MGENはパソコン要らずのスタンドアローンオートガイダーでした。 パソコン不要で、デジタルカメラも制御できるMGENは注目を集め、デジタル一眼レフカメラユーザーを中心に一気に広まりました。
冷却CMOSカメラメーカーのZWO社から、カメラや赤道儀を制御できるASIAIRが発売開始されました。 タブレットやスマホから天体撮影をコントロールできるとあって、徐々に注目を集め、天体撮影方法の一つの主流になりました。
2023年現在は、パソコンを使ってオートガイダーをコントロールするユーザー、 ASIAIRを使用してタブレットやスマホからオートガイド撮影を楽しむユーザー、 それに、MGEN-3を使ってスタンドアローンで撮影を楽しむユーザーに大きく分かれています。
2023年 4月更新