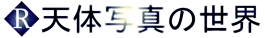追尾撮影で星空をじっくり撮ってみよう
固定撮影になれてきたら、今度は小型の赤道儀を使って星空をじっくり撮ってみましょう。 今回は星を追いかける装置「赤道儀」を使うので、何分露出しても星は点に写ってくれます。
また、追尾撮影ではデジタルカメラのCCDの同じ場所に連続的に星の光が記録されるので、固定撮影よりも暗い星が写ってくれます。 天の川や淡く輝く星雲もしっかり写ってくれるのが、こうした追尾撮影の魅力です。
赤道儀は追尾撮影に必要なアイテム
 追尾撮影には、星を追いかける赤道儀が必要になります。
赤道儀にはいろいろな種類がありますが、カメラ三脚よりも高価ですので結構な出費になってしまいます。
なるべく信頼できるメーカー製品を選び、末長く使うとよいでしょう。
よい赤道儀なら十数年くらいは使えると思います。
追尾撮影には、星を追いかける赤道儀が必要になります。
赤道儀にはいろいろな種類がありますが、カメラ三脚よりも高価ですので結構な出費になってしまいます。
なるべく信頼できるメーカー製品を選び、末長く使うとよいでしょう。
よい赤道儀なら十数年くらいは使えると思います。
赤道儀を選ぶ上で、追尾させるモーターが付属しているどうかも重要なチェックポイントです。 私が使っている小型赤道儀(右写真)はモーターが別売りで、その分全体として高くなってしまいます。 モーターの出費分も考えて機種を選ぶとよいでしょう。 赤道儀の極軸を正確に天の北極に合わせるための極軸望遠鏡が用意されているかどうかも、チェックしておきたい項目です。
参考までに写真の小型赤道儀は、高橋製作所の「P-2Z」という小型赤道儀です。 6キロ前後の機材を載せることが出来ますので、小型の天体望遠鏡を使った撮影にも使用しています。 詳しい情報は、撮影機材のタカハシP2赤道儀のページをご覧下さい。
広角レンズならポータブル赤道儀がお勧め
 広角〜標準までのカメラレンズと、デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮影する場合は、
容易に持ち運びできるコンパクトサイズの赤道儀(ポータブル赤道儀)がお勧めです。
広角〜標準までのカメラレンズと、デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮影する場合は、
容易に持ち運びできるコンパクトサイズの赤道儀(ポータブル赤道儀)がお勧めです。
ポータブル赤道儀は、小型赤道儀の片方の軸(赤緯体)を取り外したような形をしていて、 星の動きを追いかける一軸だけがコンパクトにまとめられています。 右写真は、ユニテック社から発売されているSWAT-200というポータブル赤道儀です。 デジタル一眼レフカメラの大きさと比べると、そのコンパクトさがよくわかると思います。
このポータブル赤道儀には様々な種類があります。 手のひらに載るほど小さな製品から、形が変わった製品まで様々です。 持ち運びを考えるとコンパクトな製品を選んでしまいがちですが、 一般的に大きいポータブル赤道儀の方が安定感が良く、追尾精度も高いので悩みどころです。 天体写真を始めたばかりのころは機材に助けられることが多いので、 少し大きめの信頼できる製品を選んでおいた方がよいと思います。
ポータブル赤道儀の中では、ビクセンから登場した小型赤道儀「ポラリエ」が人気を博しています。 その他、昔からあるポータブル赤道儀としては、スカイメモRSが有名です。 スカイメモRSには極軸望遠鏡も内蔵されていて、強度と精度のバランスがよいので、 ベテラン天体写真ファンにもよく使用されています。 これらの赤道儀の詳しい性能については、ポータブル赤道儀の比較ページをご覧下さい。
赤道儀にデジタルカメラを取り付けてみよう
 赤道儀を購入したら、まずはマニュアルを読みながら自宅で使い方を練習しておきましょう。
赤道儀は、慣れないうちは少し使いにくい機械ですが、触っているうちに動き方などが分かってくると思います。
シンプルな機械ですから、どなたでも使いこなせると思います。
赤道儀を購入したら、まずはマニュアルを読みながら自宅で使い方を練習しておきましょう。
赤道儀は、慣れないうちは少し使いにくい機械ですが、触っているうちに動き方などが分かってくると思います。
シンプルな機械ですから、どなたでも使いこなせると思います。
扱いに慣れてきたら、一度デジタル一眼レフカメラを赤道儀に取り付けてみましょう。 この時注意したいのが、カメラ三脚と違って赤道儀はカメラを直接取り付けるようにできていないと言うことです。 カメラ三脚で雲台を外した様な状態、と考えるとイメージし易いでしょうか。 ですので、必ず何かのアダプターが必要になります。 赤道儀を購入するときは、デジタル一眼レフカメラを取り付けて撮影したい旨を伝えて、必要なアダプター類も同時に購入しておきましょう。
ポータブル赤道儀にデジタル一眼レフカメラを取り付ける場合には、自由雲台が便利です。 自由雲台にも様々な種類がありますが、少し強度が高い製品を選んでおくと安心です。
デジタル一眼レフカメラを赤道儀に取り付けたら、モーターを動かして正常に動くか確認してみましょう。 この時注意する点は「モーターが正常に動いているか」、「架台にがたつきがないか」などです。 追尾精度などは実際に星を写してみないとわかりませんが、これらの点は本番撮影前に自宅で確認しておきましょう。 もし問題があれば、販売店に連絡して早めに対処してもらうことも大切です。
慣れないと難しい極軸合わせ
 赤道儀という機械は、ある軸を中心にして回転することで星を追いかける装置です。
ということは、その回転軸がずれていると、星を追いかける動きもずれてしまいます。
この軸のことを極軸と呼んでいます。
そしてその極軸の方向は、正確に天の北極の向きに一致していなければなりません。
天の北極というと難しそうですが、なんのことはなく、北極星の方向のことです。
赤道儀という機械は、ある軸を中心にして回転することで星を追いかける装置です。
ということは、その回転軸がずれていると、星を追いかける動きもずれてしまいます。
この軸のことを極軸と呼んでいます。
そしてその極軸の方向は、正確に天の北極の向きに一致していなければなりません。
天の北極というと難しそうですが、なんのことはなく、北極星の方向のことです。
最近の赤道儀には、右写真のような極軸望遠鏡が取り付けられています。 この小さな望遠鏡を覗いて、赤道儀の軸を天の北極に向けます。 導入の方法はマニュアルを見て頂くとして、少し注意する点があります。 それは正確な天の北極と北極星は、ほんの少しだけずれているということです。 ですから、真北を向いていて動かないと言われる北極星も、実際には天の北極の周りを小さな円を描いて回っているのです。
それを考慮すると、極軸望遠鏡の中心に北極星をもってくるだけでは十分ではありません。 それに対処するため、たいていの極軸望遠鏡には、時間と日付を合わせると「北極星をここに入れてくださいよ」ということを示すスケールが入っています。 そのスケールに従って北極星を導入し、極軸を天の北極に合わせてみましょう。
少し面倒ですが、この設定がデジカメ撮影中の赤道儀の追尾精度を左右します。 焦らずにゆっくり合わせましょう。 文字で書くと難しそうですが、順を追ってやってみると、だんだんとわかってくると思います。
※ポータブル赤道儀の場合には、一般的に極軸望遠鏡は内蔵されておらず、 本体に開けられた「のぞき穴」を使って極軸を合わせます。
まずは広角レンズや標準レンズで撮影してみよう
 星を追いかける追尾撮影と言っても、焦点距離の長いレンズを使って撮影すると、星が少し流れてしまうことがあります。
まず初めは、広角レンズや標準レンズクラスのカメラレンズを使って、追尾撮影に慣れていきましょう。
最初から無理するとなかなかうまくいきません。
慣れてから、難しい撮影にステップアップさするのが上達への近道です。
星を追いかける追尾撮影と言っても、焦点距離の長いレンズを使って撮影すると、星が少し流れてしまうことがあります。
まず初めは、広角レンズや標準レンズクラスのカメラレンズを使って、追尾撮影に慣れていきましょう。
最初から無理するとなかなかうまくいきません。
慣れてから、難しい撮影にステップアップさするのが上達への近道です。
カメラレンズは固定撮影の時と同じく、明るいレンズが理想ですが高価です。 まずはお手持ちのカメラレンズで十分です。 最近のズームレンズは性能がよいので、星空撮影に十分に使うことができます。 こうしたレンズをどんどん星空撮影に使ってみましょう。
ピント合わせは固定撮影と同じ方法で行います。 短い露出時間で撮影して、デジカメの液晶モニターでピント位置を確認する方法です。 お使いのデジタル一眼レフカメラにライブビュー機能があれば、 それを使ってより簡単にピント合わせができるでしょう。 できれば、液晶画面を拡大できる数倍のルーペがあると星の大きさがよくわかってよいでしょう。
天の川を追尾撮影で狙ってみよう
 デジタル一眼レフカメラを取り付けました。極軸合わせもOK。後はデジカメのシャッターを押すだけです。
でもその前に、赤道儀のモーターを動かすのを忘れないようにしてください。
赤道儀にデジカメを載せていても、赤道儀のモーターが動いていないと星は流れて写ってしまいます。
デジタル一眼レフカメラを取り付けました。極軸合わせもOK。後はデジカメのシャッターを押すだけです。
でもその前に、赤道儀のモーターを動かすのを忘れないようにしてください。
赤道儀にデジカメを載せていても、赤道儀のモーターが動いていないと星は流れて写ってしまいます。
星空は広いのでいろいろな撮り方がありますが、まずは天の川を撮ってみましょう。 天の川は、夏ならさそり座付近、冬ならオリオン座の辺りでボンヤリ輝いています。 この辺りを撮ると、たくさんの星や星雲が写って見応えがある写真に仕上がります。 秋ならカシオペア座付近を撮ると、秋のうっすらした天の川が写って美しいと思います。
最初は失敗がつきものですから、まずはおおよその方向を合わせて撮ってみましょう。 最近のデジタル一眼レフカメラをお使いなら、ISO1600に設定して5分露出を基本とすればよいでしょう。 まずはその設定で撮影してみてから、画像をモニタでチェックしてみましょう。 「星は流れていないか」「ピントは合ってるか」が大きなポイントです。星がもし流れていたとしたら、 赤道儀の設定や調子が悪いのかもしれません。その辺りを再チェックしてみましょう。
追尾撮影が上手くいくと、星が輝く綺麗な星空を撮ることが出来ます。 星は点像で美しく、その場所で見た星空の記憶を自分で撮った写真が呼び覚ましてくれるでしょう。 固定撮影に慣れてきたら、是非チャレンジしてみていただきたい撮影方法です。
※具体的な撮影方法を説明した、ポータブル赤道儀で星空撮影のページも是非ご覧下さい。
 |
ビクセンポラリエ
株式会社ビクセンが2011年に発売開始したポータブル赤道儀が「ポラリエ」です。 発売開始と共にヒット商品となり、一時は注文しても在庫がなかったほどです。 ポラリエはコンパクトですが、力強いモーターが使われているので安心して撮影を楽しめます。 ただ電池のもちが悪いので、予備の電池はいつも携帯しておくようにしましょう。 ポラリエはユーザーが多いので、望遠鏡販売店ではオリジナルのオプションパーツが販売されています。 こうしたパーツを利用して、自分だけのポータブル赤道儀を組み立ててみるのも面白いのではないでしょうか。 |