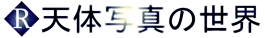タカハシε-160の使用レビュー
高橋製作所のイプシロン160(ε-160)望遠鏡は、1984年に高橋製作所が発売開始した天体望遠鏡です。 このε-160は、観望するための天体望遠鏡ではなく、天体写真撮影用に作られた望遠鏡で「アストログラフ」と呼ばれています。 私のε-160は2003年に限定で再生産されたときに購入したモデルで、鏡筒色は下のような白色でした。

タカハシε-160の概要
タカハシε-160は、高橋製作所が開発したイプシロン光学系を使用した反射望遠鏡です。 イプシロン光学系は、ニュートン反射と同じような構造をしており、 双曲面鏡で集めた光を接眼部に設置した補正レンズを使って、収差補正する光学設計になっています。 ニュートン反射と同じように光軸調整ができるので、アストログラフとしては使い勝手が良いのが特徴です。
2018年現在、高橋製作所は、タカハシε-180EDとε-130Dを製造していますが、 昔は、ε-130から大型のε-350まで、幅広いラインナップがありました(大型機は今でも受注で生産しています)。
タカハシε-160は、小さなモデルチェンジを繰り返しながら生産が続けられていましたが、 2002年頃に生産終了となりました。 当時、生産が終了した理由は、 ラージフォーマットの銀塩フィルムが使える高性能屈折望遠鏡に人気が集まり、売れなくなったためです。 生産終了当時は、中古のε-160が8万円前後で販売されていました。
 銀塩中判フィルム時代は、中古市場でも人気がなかったε-160ですが、
デジタル一眼レフカメラが天体撮影に用いられるようになってから、再び脚光を浴びるようになりました。
銀塩中判フィルム時代は、中古市場でも人気がなかったε-160ですが、
デジタル一眼レフカメラが天体撮影に用いられるようになってから、再び脚光を浴びるようになりました。
その理由は、デジタル一眼レフカメラで長時間露光するとノイズが増えるため、 F値の明るい鏡筒が有利だったことと、色収差が発生する屈折式が嫌われたためです。
また、中判銀塩フィルムカメラが用いられていた頃と異なり、 デジタル天体撮影では、APS-Cサイズのセンサーが主流になったため、 イメージサークルの大きな望遠鏡が必要なくなったことも理由の一つでしょう。 εシリーズに注目が集まるに従い、中古市場の価格は一気に上がり、 ε-160は20万円ほどで取引されるようになりました。そんな中、ユーザーの熱い要望に答えた高橋製作所が、限定で再生産したのが、私が使っていたε-160です。 鏡筒色はオレンジ色からホワイトに変更され、補正レンズもマルチコート化されて透過率が上がった製品が採用されました。 スペック表では、性能は従来機とほとんど変わりませんが、限定生産品ということで、希少価値の有る鏡筒でしょう。
非常にシャープなタカハシε-160
タカハシε-160アストログラフの最大の武器は明るさ(F値)です。 この明るさから得られる広い写野が、デジタル一眼レフカメラや冷却CCDカメラを使った星雲星団の撮影に適しています。
実際に撮影に写っている星は、色収差がなく、シャープで気持ちの良い星像です。 周辺像もAPS-Cサイズのデジタル一眼レフカメラなら問題ありません。 ただ35ミリフルサイズの冷却CCDカメラを取り付けると、端の方の星は放射状に流れてしまいます。
私はST2000XMデジタルカメラと組み合わせて使っていましたが、 このカメラのピクセルサイズとε-160の解像度の相性はとても良く、 優れた作品をたくさん撮ることが出来ました。
タカハシε160とε180ED
 タカハシε-160ユーザーにとって気になるのが、2005年に発売開始されたタカハシε180EDの存在ではないでしょうか。
タカハシε-160ユーザーにとって気になるのが、2005年に発売開始されたタカハシε180EDの存在ではないでしょうか。
ε-180EDは、補正レンズにEDレンズを用いて、F値をF2.8まで明るくしたイプシロン史上最も明るいアストロカメラです。 明るさの面では、ε160に勝ち目はなさそうです。 実際に同じデジタルカメラを使って撮影し、画像の写りを比べてみましたが、 明るさの面ではε-180EDの方が優れていました。
しかし、両方の鏡筒を使って見ると、ε-160が優れていた点も確認できました。 ε-160の方が、後発のタカハシε-180EDよりも、中心の星像が小さく収まっていたことです。 これは副鏡の遮蔽率の違いと、スパイダー太さによる光の回折によるところが大きいのだと思います。 実際に撮影してみないとわからない微妙な違いだと思います。
一方、撮影画像の周辺像となると、タカハシε180EDの方が圧倒的によくなります。
特にフルサイズのデジタルカメラを取り付けると、ε160では星が隅で放射状に流れてしまいますが、
ε180EDでは星像の乱れはあまり目立ちません。
フォーマットの大きなデジタル一眼レフカメラを使われるなら、後発のタカハシε180EDがお勧めでしょう。
※限定発売されたε-160用デジタル補正レンズを用いると、ε-160の周辺像は改善されます。
光軸の合わせやすさという面では、少しF値が暗いタカハシε-160の方が楽でした。 接眼部の平面性(スケアリング)も、それほど気にしなくて良いので精神的に楽です。 あまり比べてもいけませんが、こうした点は、ε160の方が良かった点でしょう。
タカハシε160の光軸調整
 タカハシε160の初期モデルには、丸棒スパイダーが使われていましたが、
後期のモデルとこの限定生産モデルには、羽根型スパイダーが使われています。
タカハシε160の初期モデルには、丸棒スパイダーが使われていましたが、
後期のモデルとこの限定生産モデルには、羽根型スパイダーが使われています。
光軸の調整機構自体は、タカハシMT-160に使われていたものと同じ構造です。 斜鏡には3本の押しネジと1本の引きネジが装備され、 主鏡セルには3つの押し引きネジが付けられています。
鏡筒先から覗くと、斜鏡が接眼部の反対側にオフセットされているのがわかります。 ε160の主鏡は押さえ爪で主鏡セルに固定されていますが、この爪部分が出っ張っているためにここで光が回折し、 輝星の像が悪化します。 これを避けるため、主鏡セルの上に丸いマスクを自作して貼り付けています。 このマスクは、1ミリ厚のアルミ板をサークルカッターで切って作ったもので、 つや消し塗装して余計な反射を防いでいます。
光軸調整は、タカハシの光軸調整用センタリングアイピースとレーザーコリメーターを使って行っています。 まずセンタリングアイピースとチューブを使って、斜鏡の前後位置を斜鏡のセンターマークを頼りにして調整します。 その後センタリングチューブを外して、斜鏡が接眼部にしっかりと向いているかを確認します。 この向きを調整できたら、レーザーコリメーターを接眼部に取り付け、レーザーを照射します。
レーザーを照射すると主鏡上にレーザーの赤い点が表示されるので、 それが主鏡のセンターマーク中心に来るよう、斜鏡の傾きを調整します。 傾きを調整すると斜鏡の回転がずれることがあるので、またセンタリングアイピースに替えて確認します。 この作業を何回か繰り返して、どちらも問題なくなったら、主鏡の調整へと移ります。
主鏡の調整は、センタリングアイピースの中心に主鏡のセンターマークが来るようにするだけです。 主鏡セルには、押しネジと引きネジが一対になって取り付けられているので、それを使って傾きを調整します。 すべて終了したら、レーザーコリメーターを使ってレーザー光が主鏡センターに当たって、 接眼部の照射点に戻ってきているかどうかを確認して光軸調整を終えます。
なお、スパイダーの長さ調整については、むやみに触ると大きくずらしてしまう原因になると思っています。 スパイダーは、鏡筒側面から中心までの長さを測って、スパイダーの交差点が鏡筒の中心来ていればOKと判断しています。 それよりも、主鏡セルが、鏡筒のどちらかに寄ってしまっている方が問題に感じています。 私は主鏡セルの隙間にアルミ板を挟んで、主鏡が偏らないようにしています。
タカハシε-160のスペック
タカハシε-160アストログラフの仕様を以下に示します。
| 名称 | ハイパーボライドアストロカメラε-160 |
| 有効口径 | 160mm |
| 焦点距離 | 530mm |
| 口径比 | 1:3.3 |
| イメージサークル | 43mm |
| 鏡筒径 | 204mm |
| 鏡筒全長 | 586mm |
| 重量 | 約8kg |