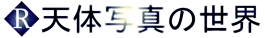キヤノンEF24mm F1.4L II USMレビュー
 キヤノンEF24mmF1.4L II USMは、開放F値が1.4と非常に明るい広角レンズで、2008年冬に発売開始されました。
キヤノンEF24mmF1.4L II USMは、開放F値が1.4と非常に明るい広角レンズで、2008年冬に発売開始されました。
このEF24mmF1.4LIIUSMレンズは、1997年から販売されていたⅠ型を改良したレンズで、より高性能を狙った高級レンズです。 前モデル同様、開放F1.4の明るさが魅力のレンズで、新型レンズでは非球面レンズとUDレンズがそれぞれ2枚用いられています。 また、レンズのコーティングにもSWCコーティングが施され、ゴーストやフレアに有効な対策が施されています。
実勢価格は20万円弱と非常に高価なレンズなのですが、24ミリという使い易い画角とF1.4の明るさで、 星景写真ファンから人気があるレンズです。 今回、このレンズで星空を撮影することができたので、周辺減光の様子と星像について検証してみました。
キヤノンEF24mmF1.4LIIUSMの概要
キヤノンEF24mmF1.4LIIUSMは、EFレンズの中でも特に明るい単焦点レンズで、光量の少ない星空撮影などで活躍が期待されるレンズです。 レンズにはSWCコーティングが施されているので、輝星の周りのゴーストの低減も期待されます。 キヤノンのレンズラインナップには、同じ焦点距離で開放F値が2段暗い、EF24mmF2.8レンズがありますが、 こちらとは価格で5倍弱の開きがあります。
広角の単焦点レンズですが、レンズの鏡体は大きくなっています。 また、重量も650gと重く、標準ズームレンズのEF24-105mmF4Lレンズとほぼ同じ重さがあります。 天体撮影に人気のEOSKissシリーズと組み合わせて使うと、レンズ側が重くなり、バランスに欠けるのが少々残念です。
最短撮影距離は0.25m、フィルター径は77ミリです。 製品にはフードが付属します。高級レンズだけ合って防塵・防滴構造となっています。
 |
 |
一般撮影での印象
 キヤノンEF24mmF1.4LIIUSMをAPS-Cサイズのデジタル一眼レフカメラに装着すると、35ミリ換算で焦点距離が38mm相当となるので、
スナップ撮影に使い易い画角となります。
そこで、少し贅沢ですが、キヤノンEOSKissX3と組み合わせて人物や景色をまず撮影してみました。
キヤノンEF24mmF1.4LIIUSMをAPS-Cサイズのデジタル一眼レフカメラに装着すると、35ミリ換算で焦点距離が38mm相当となるので、
スナップ撮影に使い易い画角となります。
そこで、少し贅沢ですが、キヤノンEOSKissX3と組み合わせて人物や景色をまず撮影してみました。
一般撮影に使用してみると、ズームレンズとは違ったクリアな像を結んでくれました。 広角レンズですが、開放F値が明るいので背景ボケも楽しめるのが魅力で、絞ればパンフォーカスの写真を楽しめます。 開放で撮影すると周辺減光が出ますので、ポートレート撮影などでボケを活かす場合でも、半絞り~1段程度は絞った方がよい印象でした。 像面歪曲が少ないレンズなので、建物などを写しても歪みが少ないのは良い点です。
ところで、このレンズを使い始めた当初、EOSKissX3と組み合わせるとピントがきていないことが多かったので、 レンズをメーカーに点検に出しました。 点検によれば、レンズではなくカメラボディの問題のようで、カメラの修理後は開放でもピントが合うようになりました。 明るいレンズですので、ボディのAF精度にも注意が必要なのかもしれません。
星空撮影での印象
キヤノンEF24mmF1.4LiiUSMとキヤノンEOS5Dを使用して星空を撮影してみました。 まずは周辺減光の様子です。左は絞り開放で撮影した画像で、右は一段絞ってF2で撮影したもの、 その下はF2.8とF4に絞って撮影した星空写真です。 露出時間は背景濃度が同じ位になるよう調整しています。また、どれも周辺減光補正などの画像処理はしていません。 撮影には小型赤道儀を使用しています。
| 絞り開放で撮影 | 絞りF2で撮影 |
 |
 |
| 拡大画像へのリンク | 拡大画像へのリンク |
| 絞りF2.8で撮影 | 絞りF4で撮影 |
 |
 |
| 拡大画像へのリンク | 拡大画像へのリンク |
小さな画像では分かりづらいですが、絞り開放の画像は中央部が明るくなり、周辺部がかなり暗くなっています。
それと比較すると、一段絞ると周辺減光が減っているのがわかります。
また、2段絞ると明るさはよりフラットになり、3段絞ると四隅を除いて光量がほぼフラットになります。
この結果からすると、星空撮影では周辺減光が気になることが多いので、1段は絞って撮影した方が良さそうな印象を受けました。
※リンク先の大きな画像もご覧下さい。
続いて気になる星像ですが、それぞれのF値に絞ったときのピクセル等倍画像を下に掲載しましたのでご覧下さい。
| 絞り開放で撮影 | 絞りF2で撮影 | 絞りF2.8で撮影 | 絞りF4で撮影 | |
| 中心像 |  |
 |
 |
 |
| 右上隅の星像 | 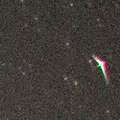 |
 |
 |
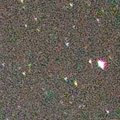 |
| 左下隅の星像 | 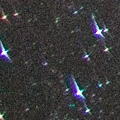 |
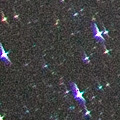 |
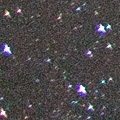 |
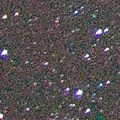 |
中心像は絞り開放から、なかなかシャープです。 明るい星の周りのパープルのフリンジもほとんど気になりません。 一段絞ればよりシャープになります。
写野周辺の星像を見ると、絞り開放では星に大きなコマが発生しているのがわかります。 この星像の収差は、絞りを1段絞ってもそれほど改善せず、2段絞って若干改善する程度です。 3段絞ってF4で撮影すると、写野周辺までほぼ良好な星像になりますが、ここまで絞ると明るいレンズを使うメリットが感じられません。
絞り開放時での周辺星像の流れ方は大きく、また、写野中心から少し離れた点でもコマが発生するので、 絞り開放で星空を撮影するのは現実的でない気がします。 綺麗な星像で撮影しようと思えば、少なくとも1段は絞って撮影した方が良さそうです。 下に絞り開放(F1.4)で撮影したときの、各点での星像をピクセル等倍で載せてみました。

| ポイント1 | ポイント2 | ポイント3 | ポイント4 |
 |
 |
 |
 |
この画像を見ると、絞り開放で撮影したときの星像の流れ方が、写野周辺に近づくにつれて大きくなっているのがわかります。 今回はフルサイズのデジタル一眼カメラで星空を撮影しましたので、 センサーサイズが小さなAPS-Cサイズのデジタル一眼レフカメラとEF24mmレンズを組み合わせると、 画角が狭くなるので、開放で撮影しても周辺の収差はもう少し目立たなくなると思われます。
キヤノンEF24mmF1.4LIIUSMを星空撮影に使った印象
キヤノンEF24mmF1.4LIIレンズは開放F値が明るいので、ファインダーが明るく、星空撮影では暗い星まで確認できます。 そのため、星空のような暗い環境でも構図の確認が行いやすいのは大きなメリットです。 デジカメの最高感度と開放絞りと組み合わせれば、ほんの十数秒で星々が写って来るので、試写して構図の最終確認も容易にできます。
贅沢なレンズ設計ため、ボディ本体は大きく、重量も高性能標準ズームレンズ程あります。 フルサイズデジタル一眼レフカメラと組み合わせると結構な重量があるので、ポータブル赤道儀と組み合わせて撮影するときには、 使用する雲台の強度に注意した方が良さそうです。
レンズの周辺像は購入前に思っていたよりも悪く、開放絞り付近では大きく乱れてしまいます。 絞りを2段から3段絞れば、フルサイズ全面で良好な星像となりますが、このレンズの明るさを生かせないのが難点です。 24ミリ前後の焦点距離のレンズは星空撮影に使い易いのですが、どのメーカーのレンズも周辺では収差が目立ちます。 開放絞りで全面シャープなレンズがあれば、星空撮影には最高なのですが、設計上なかなか難しいのでしょう。
このEF24mmレンズの全体の印象としては、一般撮影での逆光時や難しいシーンでは写りが良いのですが、 星空を写したときの周辺星像に関しては、思っていたほどの写りではなかったというのが正直な感想です。 しかしせっかく手に入れたので、流星群の撮影など、レンズの明るさが生かせるシチュエーションで活躍させていきたいと考えています。
キヤノンEF24mmF1.4L2USMのスペック
| 名称 | キヤノンEF24mmF1.4L II USM |
| 焦点距離 | 24mm |
| レンズ構成 | 10群 13枚 |
| 絞り羽枚数 | 8枚 |
| 最短撮影距離 | 0.25m |
| フィルター径 | 77ミリ |
| 大きさ | 86.9mm×83.5mm(最大径) |
| 重量 | 650g |
 |
ビクセンポラリエ
株式会社ビクセンが2011年に発売開始した、ポータブル赤道儀ポラリエ。 今までの赤道儀の概念を覆す斬新なデザインで、発売開始と共にヒット商品となりました。 こうしたポータブル赤道儀を一つ持っておかれると、星空撮影の幅が広がります。 ポラリエはユーザーが多いので、望遠鏡販売店によっては、オリジナルのオプションパーツを販売しています。 こうしたパーツを利用して、より使い易い自分だけのポラリエを作ってみるのも面白いのではないでしょうか。 |
※追尾撮影にチャレンジのページに、小型赤道儀を使った星空撮影方法をまとめていますので、そちらのページも是非ご覧下さい。